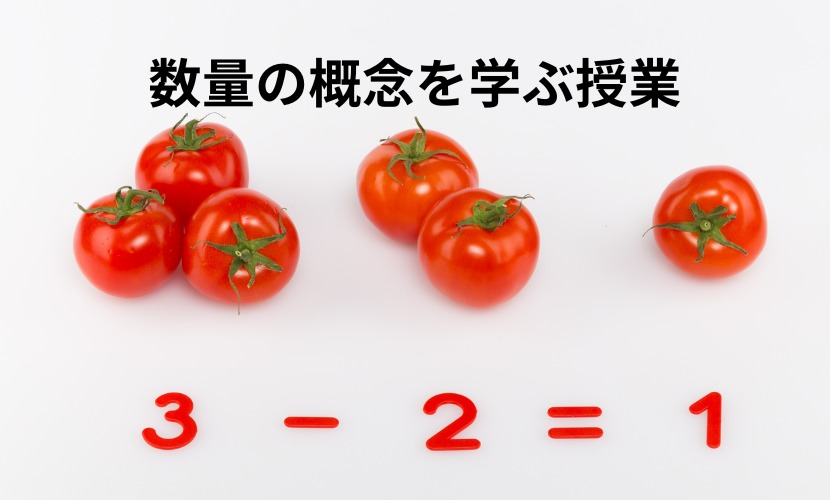幼児、低学年の時期の算数の学び方によって、その後の学習が大きく変わっていきます。
「うちの子には無理」
「勉強なんてまだ早い」
と言っているうちに、あっという間に子どもは成長し、受験期になって慌てる親も少なくないです。
未就園児の指導
未就園児の子ですと、まだまだ鉛筆は持たずに、しっかりと指先を使っていきます。
「これはオレンジ色、これはピカピカしてる、同じ色並べてみよう」
楽しそうに沢山喋ってくれます。
きれいに枠に収まるように、10個ずつ並べていくことがポイント。
具体物を使って、数の概念を少しずつ入れていき、五進法、十進法の土台を学んでいきます。
数字だけでなく、数量、量感をいれていくことが大事ですよ☺️
数字を言えるのは、ただ覚えているだけです。
天秤を使えば、体験的に「軽い・重い」を学べます。
また、おもり同士を比べて『実数と実数』の理解につなげます。
幼児さんこそ丁寧に丁寧に、算数の基礎となる概念を入れていきます。
小さな頃からペーパー暗記学習ばかりしなくて大丈夫です。
数量の概念がバチッと入った子は、一気に伸びてすぐ追い越して行きます😆
年少児の指導
ある日の年少さん。
新しい環境にまだ慣れないのか、お母さんと別れたくないとグズグズでしたが、別れた後はさっさと着席😆
これ、あるあるです。
幼く、親の前では甘えていても、いざ一人になると気持ちの切り替えが出来るんです。
「先生、お勉強するよ!!」とまで言い出して・・・🤭
今日も試行錯誤しながら、数理色板をあっという間に完成✌️
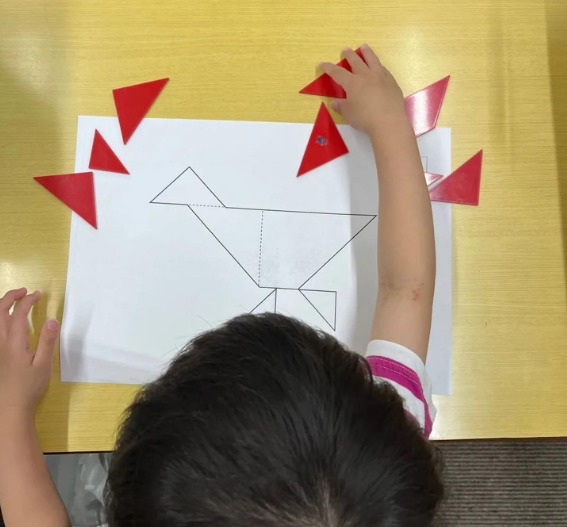
ポイントは決して教え込まないこと。
算数をとくことで一番大事なのは、試行錯誤する事です。
ここから、数の概念も獲得していきます😉
暗記とは別次元ですよ。
年中児の指導
まだ幼いからこそ、具体物を自身で動かして、目で見てじっくり進めて行きます。
決してペーパー上だけの数字とならない様に、頭に数量のイメージができる様に丁寧にゆっくりと😉
数の分解の問題ですが、
「こっちが僕、こっちは先生のね。先生食いしん坊だから沢山りんごあげるね」
ば、ばれてる?🤣
「点描写」の問題では、
図形と線をしっかりと把握し(インプット)
頭の中でイメージをつくり(脳内処理)
イメージを正確に書き写す(アウトプット)
ことが必要とされます。
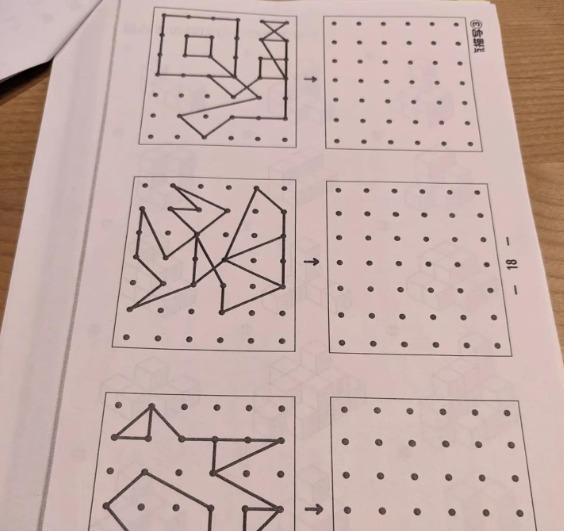
点描写によって「注意力」「構成把握能力」「作業能力」「筆圧」「指先の調整能力」などの知能因子のチェックを一度に行うことができるので、よく小学受験でも出題されますよ😉
特に、図形関連の能力とは深い関係があるので、幼児期におすすめです😀
小学低学年の指導
低学年は親御さんが迎えに来られる場合が多く、授業後はすぐ帰られます👋
そんな中「もう少し勉強してから帰ります!」と、黙々と勉強する2人😳
親御さんもそれを見越して、遅く迎えに来られます。
もし早く迎えに来られていても、そっと見守り、声掛けせずに待っています。
生徒さんも親御さんも、その関係性にも脱帽です。

小1塾生の親御さんとの世間話です。
「同級生の子は、○○でもう分数を勉強しているそうなんです。本当に小1で必要ですか?」
ん?
小1ですよね?
分数の概念を分かってやってるのかな…?
「でも久々に足し算や引き算のプリントすると、やり方忘れてるそうです」
ん???
やり方忘れるって、そもそも足し算も引き算も理解していないですよね(汗)
確かに計算は大事です。
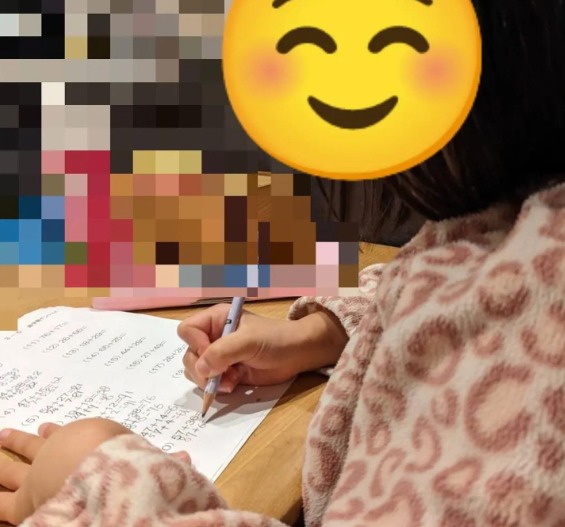
ですが、なぜそうなのか概念も理解せずに、『こうやるものなんです!』ってテクニックだけで進めるって…ため息ものでした。
我が子が勉強に困らないようにしたい!と思われる親御さん、
算数が抜群にできるようにさせてあげたいと思う方、
「算脳トレ」ってどんな授業だろう?と思ったら、まずは体験をしてみてください。